同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、賞与(ボーナス)について、基本的な考え方を取上げます。
賞与(ボーナス)
賞与(ボーナス)の性質・目的は、会社の実態によって様々です。一般的に、賞与は、以下のような形で、支給されていることが多いと思います。
一般的な賞与の支給(算定)方法
賞与算定の基礎期間を決めた上で、会社の業績や労働者の出勤率・成績評価を基に、各労働者の支給額を決める。
上記のような一般的な賞与の性質・目的は、①賃金の後払いと②会社の業績への貢献に対する報償の2つだと考えられます。
賞与の同一労働同一賃金の基本的な考え方
賞与についても、性質・目的に応じて、非正規労働者にもその性質・目的に応じて、均等又は均衡に支給する必要があります。
たとえば、賞与が、会社の業績への貢献に対する報償である場合、正社員と非正規労働者で、会社の貢献が同じであれば、同じ支給をする必要があります。一方、正社員と非正規労働者で、貢献に相違がある場合は、相違に応じた支給をしなければなりません。たとえば、非正規労働者の会社への貢献が正社員の80%だと評価できる場合は、正社員の賞与の80%を非正規労働者に支給することになります。
賞与が、過去の勤務状況に関わらず、支給日に在籍している労働者に、一定額を支給する場合は、過去の報償ではなく、将来の勤務対する勤労奨励的な性格を持っていると考えられます。そのような賞与については、支給日に在籍していて、その後も継続勤務が予定されている非正規労働者には、正社員と同じ支給をすることが必要と考えられます。
ガイドラインの考え方
ガイドラインは、以下の場合を問題ない例として、挙げています。
一方、ガイドラインは、以下の場合を問題のある例として、挙げています。
最高裁の考え方
大阪医科薬科大学事件最高裁判決は、賞与の相違も労働契約法旧20条の対象になりうることを認めています。その上で、最高裁は、賞与の労務対価の後払い、功労報償、将来の労働意欲向上等の趣旨、人材育成の確保・定着を図るという目的を踏まえ、正社員とアルバイト職員間の職務内容、配置変更範囲の相違、多数の高度業務を担う正社員の存在、正社員登用制度があることを考慮し、アルバイト職員への賞与不支給は不合理ではないと判断しました。
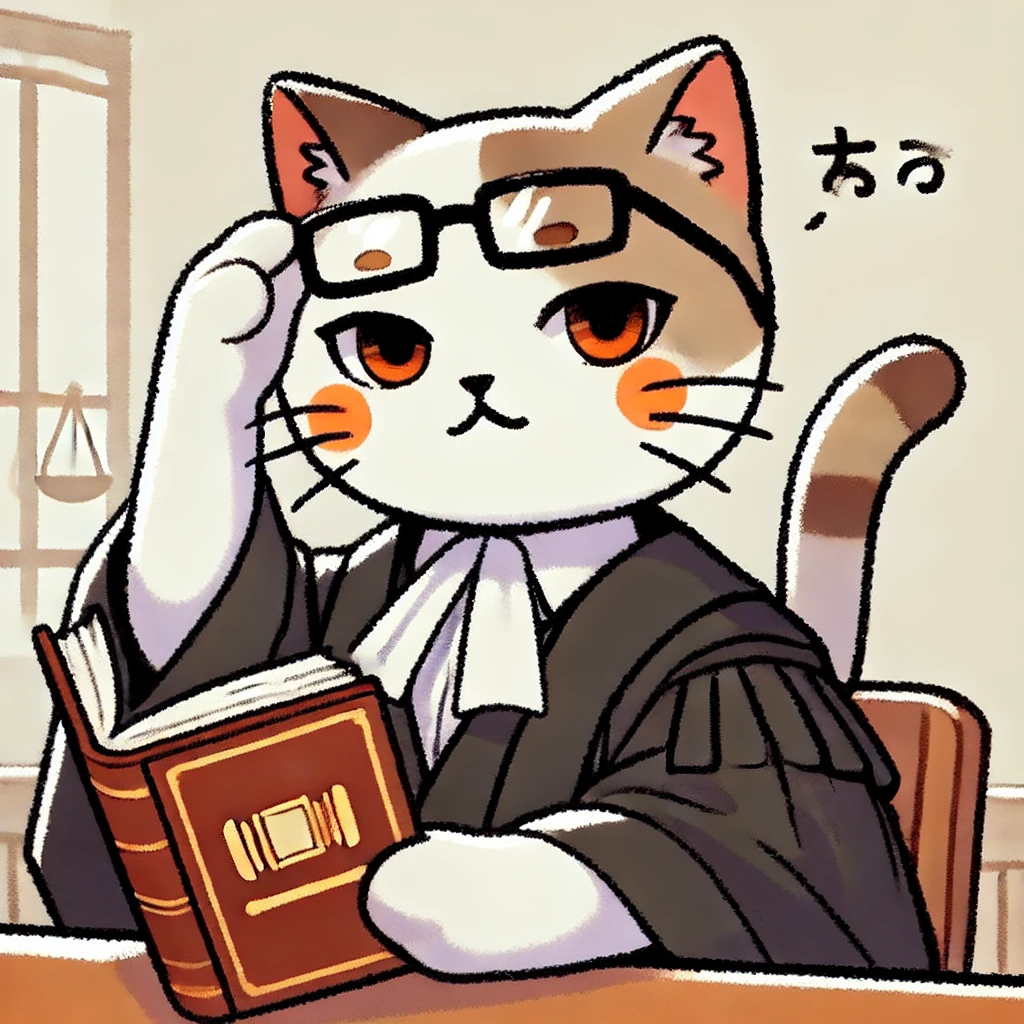
大阪医科薬科大学事件最高裁判決の詳細は、以下の「同一労働同一賃金に関する最高裁判決」を参照
同一労働同一賃金に関する最高裁判決
同一労働同一賃金に関する最高裁判決を紹介します。 有期労働契約の労働者と無期労働契約の労働者との間で、賞与・私傷病による欠勤中の賃金の支払の有無の相違が不合理な労働条件の相違か?が争われた事案です。
最高裁が、人材育成の確保・定着を図る目的を重視していることが注目されます。この考えを進めると、正社員を活用するために支給しているので、非正規労働者には支給しなくても不合理ではないとなりそうです。もっとも、労働契約法旧20条下の判例なので、パート有期法8条の解釈にそのまま妥当するのか?が今後のポイントになってくるでしょう。
最高裁の考え方を前提にすると、①正社員の経験・能力によって基本給が上がる職能給であって、②人事異動によって様々な部署で経験を積ませ長期的に人材育成を行い、③賞与の基礎が経験・能力によって上がる職能給を基礎に支給される職能給算定基礎である場合、正社員と非正規労働者の賞与の支給の相違は、不合理ではないと判断されやすいといえます。