休日労働と休日手当を取り上げます。
休日労働のポイント
休日労働のポイントは、以下の2つです。
つまり、週休二日制の場合、休日労働を行ったのが、法定休日なのか?所定休日なのか?が問題になります。
法定休日と所定休日
使用者が、休日労働の規定に従い、休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金を支払う必要があります(労基法37条1項)。
割増賃金は、法定労働時間又は週休制の基準外労働についてのみ支払い義務があります。基準内の労働には、割増賃金の支払い義務はありません。
法定休日労働は、1週間の時間外労働時間に参入されません。また、1か月60時間を超過した時間外労働は、さらに50%の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条1項但書)。
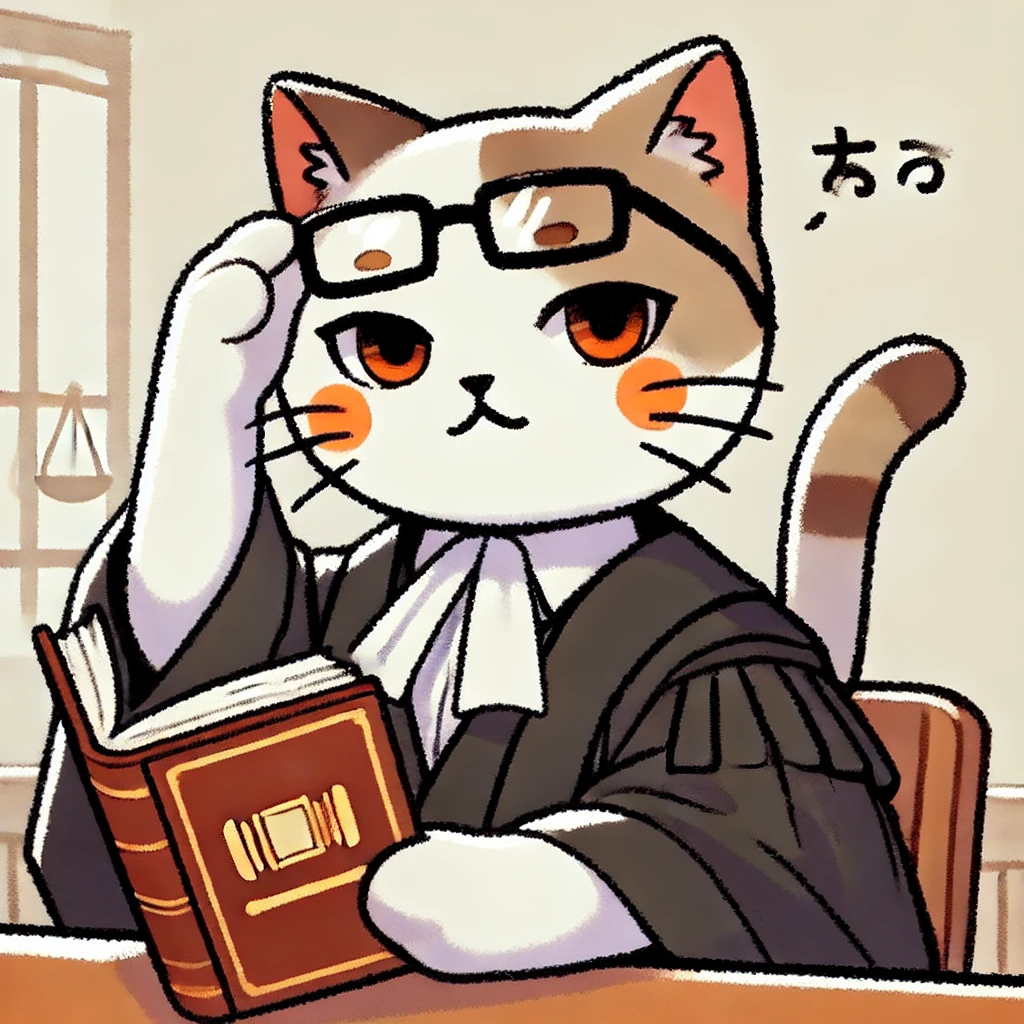
詳しくは、以下の「月60時間超過の時間外労働と代替休暇」を参照
月60時間超過の時間外労働と代替休暇(残業代の計算)
1か月の時間外労働時間数が60時間を超過すると、50%以上の割増賃金(残業代)を支払う必要があります。 この残業代の支払いに代えて、代替休暇を与えることも認められています。
この1か月60時間にも法定休日における労働は参入されません。
したがって、週休二日制の会社の場合、①法定休日と②所定休日の2つがあります。したがって、どちらが法定休日で、どちらかが所定休日かを明確にしておく必要があります。
法定休日の決め方
就業規則等で法定休日を明示していれば、その日が法定休日です。しかし、就業規則等で明示されていない会社も存在します。就業規則等で明示されていない場合は、法定休日がいつなのかが、問題となります。
1か月60時間超過に関連して、厚労省は、休日2日間労働した場合の法定休日の特定は、「当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働になる」としています。
厚労省の見解に従えば、暦週である日曜日から土曜日を基準とします。日曜日に出勤した場合、その日曜日は法定外休日で、週の最後の土曜日が法定休日ということになります。また、土曜日に出勤した場合は、日曜日が法定休日で、土曜日は法定外休日ということになります。
この理解で残業代を計算すると、計算が非常に煩雑になってしまいます。そこで、訴訟においては、日曜日を法定休日だということで、争いをなくすということも考えられます。
週休二日制の成り立ちから、もともと休日であった日曜日を法定休日とする黙示の合意があったと判断した裁判例(東京地裁平成23年12月27日判決)もあります。