民法の債権法が全面的に改正されます。今回は、主として改正によって新しくできる協議を行う旨による時効の完成猶予を取り上げます。
催告とは?
協議を行う旨による時効の完成猶予の話しの前に、まず、催告の話しをします。裁判上の請求、つまり、訴訟の提起ではなく、裁判外で、債権者が債務者に債務の履行を請求することを催告といいます(民法153条)。
催告を行った後、6か月以内に裁判上の請求・差押え・仮差押え・仮処分をしなければ、時効の中断の効力は生じません。
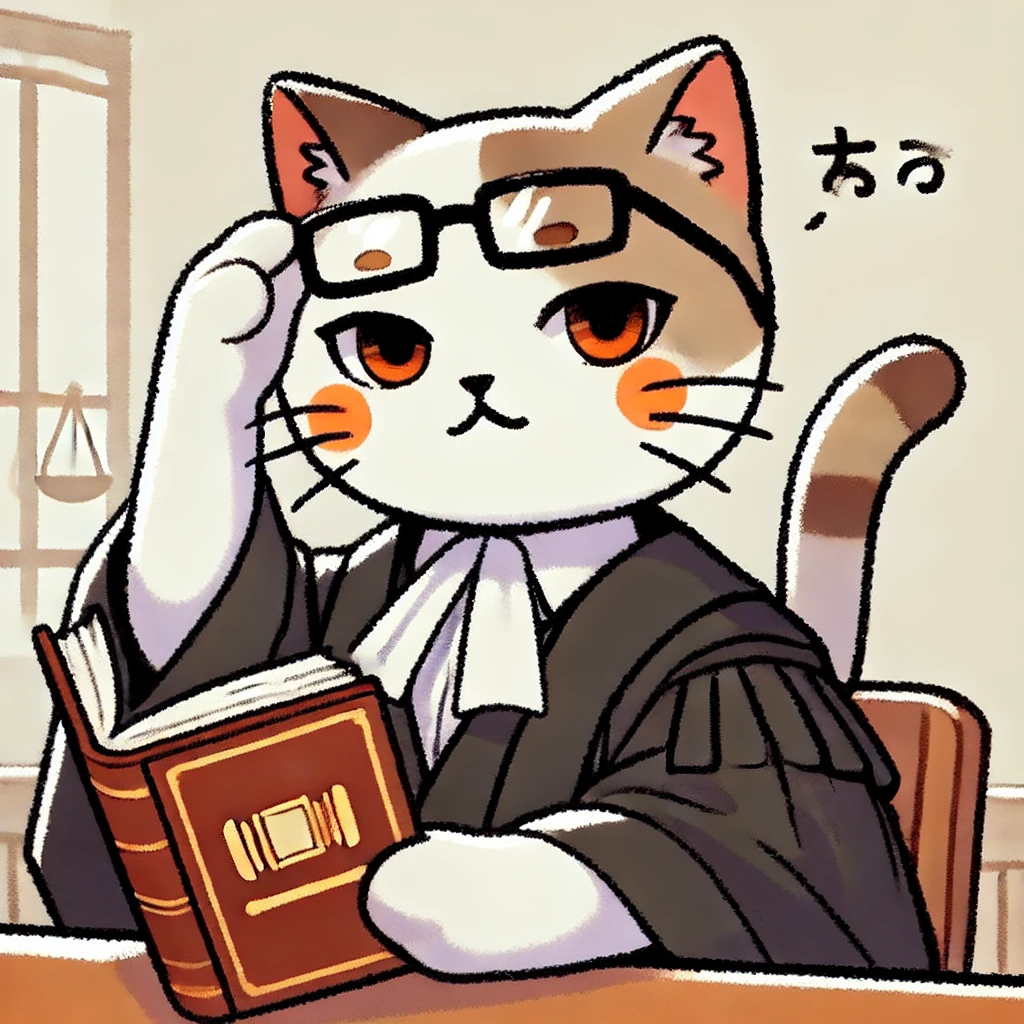
時効の中断については、以下の「民法改正と時効の更新・完成猶予」を参照
また、催告を繰り返しても時効の中断は継続しません。つまり、裁判外での請求は、時効期間が6か月延長されるという効果があるにとどまります。
改正民法での規定
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
催告は、時効の完成猶予事由です。催告を繰り返しても、意味がないことが明記されます。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
改正民法で新設されたのが、時効の完成猶予事由です。
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
権利について協議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予事由となります。ここでは、書面と規定されていますが、電磁的記録で行っても差し支えありません(改正民法151条4項)。
たとえば、交通事故で、高次脳機能障害など症状固定までに相当長期間を要するような場合に、被害者と加害者(保険会社)との間で、この合意をするといったことがあり得るのかなと思います。
時効の完成が猶予される期間
協議を行う旨の合意によって、時効の完成が猶予されるのは、次の期間のうち最も早い時までです。ただし、②の合意は、1年未満に限られます。
協議を行う旨の合意によって、時効の完成が猶予される期間
①合意した時から1年を経過した時
②当事者が合意によって定めた協議する期間
③当事者の一方が相手方に対して協議を拒絶する書面による通知をした時から6か月を経過した時
当事者が協議期間を合意しなかったとき
当事者が協議期間を合意しなかった場合は、上記の①と③のどちらか早い時まで時効の完成が猶予されることになります。
当事者が協議期間を合意したとき
当事者が協議期間を合意した場合は、上記②と③のどちらか早い時まで時効の完成が猶予されることになります。
再度の合意をすることができる
協議による時効の完成猶予で時効の完成が猶予される期間は、上記のとおりです。催告と異なり、再度、協議を行う旨の合意をすることで時効の完成を猶予することができます。ただし、完成猶予の期間は、通算で5年を超えることはできません。
催告との関係
時効の完成猶予事由である催告と協議を行う旨の合意による時効の完成は、次のとおり、二者択一となります。
催告をすでに行っている場合
催告を行っている間に、この協議を行う旨の合意をすることはできません。再度の催告はできないので、時効の完成は6か月しか猶予されません。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予中
協議を行う旨の合意によって、時効の完成が猶予されている間に、催告を行うことはできません。