2025年5月に成立した譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律のポイントを取り上げます。
譲渡担保法の成立
企業の資金調達において、不動産担保や個人保証に代わる手段として、動産(機械設備、在庫商品など)や債権(売掛債権など)を担保とする融資が活用されています。しかし、これまでの実務では、これらの動産・債権担保には明文の法律がなく、判例法理に依存していました。
このような状況に対応するため、2025年5月30日に、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)が制定されました。
譲渡担保・所有権留保とは?
譲渡担保法で対象となる「譲渡担保」と「所有権留保」は、実務で広く活用されている担保の手段です。
譲渡担保
金銭債務を担保するため、債務者などが財産(動産、債権など)を債権者に譲渡する契約です。債務者が債務者を完済すれば、担保の目的財産は債務者に返還されます。債務者が債務を返済できない場合は、債権者は目的財産から優先的に返済を受けれます。
譲渡担保の最大の特徴は、譲渡担保を設定した後も、債務者は担保の目的物を引き続き使用・収益できる点です。
所有権留保
売買契約などにおいて、代金が完済されるまで売主が目的物の所有権を留保する旨の定めがある契約です。譲渡担保と同様、買主は代金完済前でも目的物を利用できます。そのため、実務で広く活用されています。
譲渡担保法制定の背景と目的
実務で広く活用されている譲渡担保と所有権留保は、民法に直接規定はありません。その法的効力や実行方法は、判例によって形成されてきました。しかし、これにより以下のような課題がありました。
譲渡担保法は、これらの課題を解決し、法的安定性と公示性を高め、企業の円滑な事業継続と不動産担保と個人保証に頼らない資金調達を促進することを目的としています。
譲渡担保法の主な内容
譲渡担保法は、これまでの判例法理を明文化・明確化するとともに、一部の規律を合理化しています。
①担保権の対象範囲
対象となる財産は、動産、債権、その他の譲渡可能な財産が譲渡担保契約の対象です。ただし、不動産など抵当権の対象となる財産は、原則として対象外です。
②譲渡担保権者(債権者)の権限
目的財産から他の債権者に優先して弁済を受ける優先弁済権が明文化されます。
また、目的財産の売却代金や保険金など、目的財産に代わる金銭や物にも権利が及ぶ物上代位が認められます。
さらに、権利行使が妨害されている場合、その排除などを請求できる物権的請求権も明文化されます。
③譲渡担保権設定者(債務者等)の権限
目的動産を引き続き使用・収益できることが明文化されます。
後順位の譲渡担保権の設定など、余剰価値の活用が可能であることも明確化されます。
④根譲渡担保権に関する規律
被担保債権を特定せずに、債権者と債務者の間で、継続的に発生する債権を一括して担保とする根譲渡担保権に関する規律が設けられます・
元本の確定前における譲渡や分割譲渡が認められ、その登記制度が整備されます。
元本確定事由が明確化されます。
元本確定事由の例
強制執行の申立て
差押えを知ってから2週間経過
⑤集合動産譲渡担保・集合債権譲渡担保に関する規律
倉庫内の在庫をまとめて担保の目的とする集合動産譲渡担保等に関する規律が設けられます。
動産の場合は、種類と所在場所等を指定することで譲渡担保の範囲を特定します。債権の場合は、発生原因と発生時期等などを指定することで譲渡担保の範囲を特定します。
設定者の処分権限や、担保価値維持義務についても規定が整備されます。
⑥担保権の順位決定ルールと公示性の向上
同じ財産に複数の担保権が競合した場合、対抗要件(引渡し、通知・承諾、登記など)を具備した時点の先後によって順位が決まることが明文化されます。
占有改定による譲渡担保権は、外部から認識しにくいため、登記された譲渡担保権など、より公示性の高い対抗要件に劣後することが明記されます。これにより、動産に新たに担保を設定しようとする者が、既存の担保権の有無を正確に把握しやすくなります。
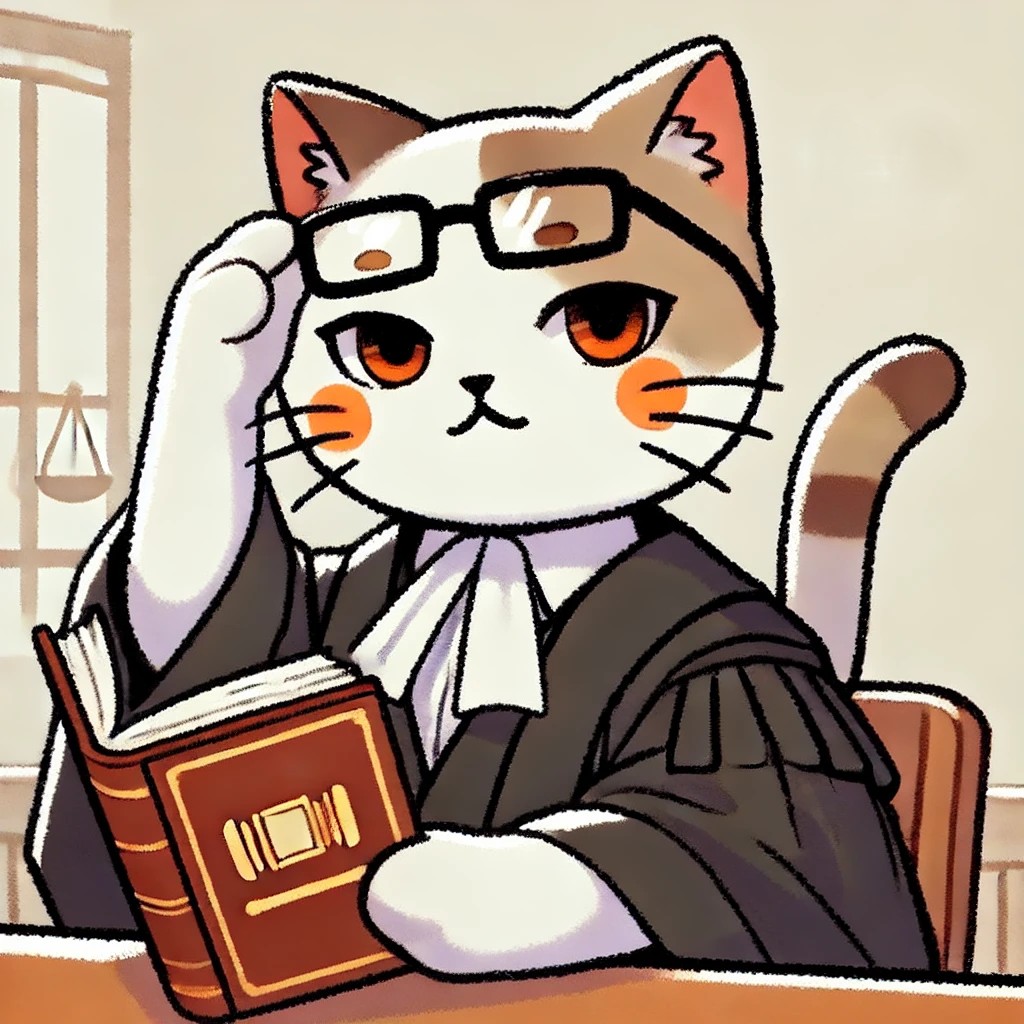
占有改定は、担保設定者が目的物を引き続き占有しながら、以後は担保権者のために占有する旨を合意することです。
目的動産との牽連性がある金銭債務(例えば、売買代金債務)を担保する譲渡担保権は、他の担保権に優先する特則が設けられます。
⑦担保権の実行方法の合理化
譲渡担保権者が裁判所の手続によらずに担保権を実行する「私的実行」ができることが明文化されます。私的実行の方式として、①帰属清算方式と②処分清算方式の2つを定め、具体的な手続が明文化されます。
私的実行の開始から完了まで、債務者の事業再生を考慮し、原則として2週間の猶予期間が設けられます。
また、動産譲渡担保権については、民事執行法に基づく動産競売など、裁判所の手続による実行も選択可能であることが明確化されます。
動産譲渡担保権の実効性を確保するため、価格減少行為の禁止などの保全処分や、目的物の引渡しを命じる引渡命令といった簡易な裁判手続が新設されます。
⑧倒産手続における取り扱いの明確化と合理化
譲渡担保権が、破産手続、民事再生手続、会社更生手において、原則として質権と同様に扱われることが明文化されます。これにより、担保権実行手続中止命令や担保権消滅許可制度の対象となります。
裁判所は、事業継続のために特に必要があると認めるときは、譲渡担保権の実行手続の禁止命令や取消命令を発令できる制度が新設されます。これは、債務者の事業再生を支援するための重要な措置です。
集合動産・集合債権譲渡担保権が実行された後、1年以内に債務者について倒産手続が開始された場合、目的財産の価値の10%を倒産財団に組み入れる制度が導入されます。これは、一般債権者の弁済原資を確保するためのものです。
倒産手続開始後に取得された動産や債権には、原則として譲渡担保権が及ばないことが明確化されます。
譲渡担保法の施行日
譲渡担保法は、公布日の2025年6月6日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されま
まとめ
譲渡担保法は、これまで判例法理に委ねられてきた譲渡担保・所有権留保の法的基盤を強化し、より予見可能で安定した取引環境を整備するものです。
特に、公示性の向上や倒産手続における新たな手続の導入は、企業の資金調達の円滑化と事業再生の支援に大きく貢献すると期待されます。