労基法の労働時間規制の例外の一つである裁量労働のみなし時間制を取り上げます。
裁量労働のみなし時間制とは?
労基法は、管理監督者(労基法41条2号)を除くすべての労働者に対して労働時間規制を適用してきました。しかし、技術革新・情報化などの変化により、労働の遂行の仕方について労働者の裁量の幅が大きく、労働時間を通常の労働者と同じように規制することが、業務の実態や能力発揮の観点から適切でない専門的な労働者が出現するようになりました。
労働遂行や時間配分に関して裁量性が高く、労働時間(量)よりも労働の成果(質)に着目して報酬を支払う労働者について、労使協定や労使委員会の決議により一定のみなし時間を定めれば、実際の労働時間にかかわらず、その時間労働したとみなす制度が、裁量労働のみなし時間制です。
専門業務型裁量労働制と企画裁量型労働制
裁量労働のみなし時間制は、①専門業務型裁量労働制と②企画裁量型労働制の2種類があります。
専門業務型裁量労働制
業務の性質上その遂行の方法を大幅に業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして省令で定める業務のうち、労使で対象となる業務を定め、労働者をその業務に従事させた場合、労使であらかじめ定めた時間労働したこととみなす制度です(労基法38条の3)。
具体的には、次の業務が省令で定められています(労基法施行規則24条の2の2第2項)。
(6)の厚労相の指定する業務には、以下の業務があります。
厚労相の指定する業務
①コピーライター
②システムコンサルタント
③インテリアコーディネーター
④ゲームソフトウェア開発
⑤証券アナリスト
⑥金融工学を用いた金融商品開発
⑦大学教授
⑧公認会計士・弁護士・建築士・不動産業者鑑定士・弁理士・税理士・中小企業診断士
専門業務型裁量労働制を採用するには、事業場において労使協定を締結し、労基署に届出る必要があります。
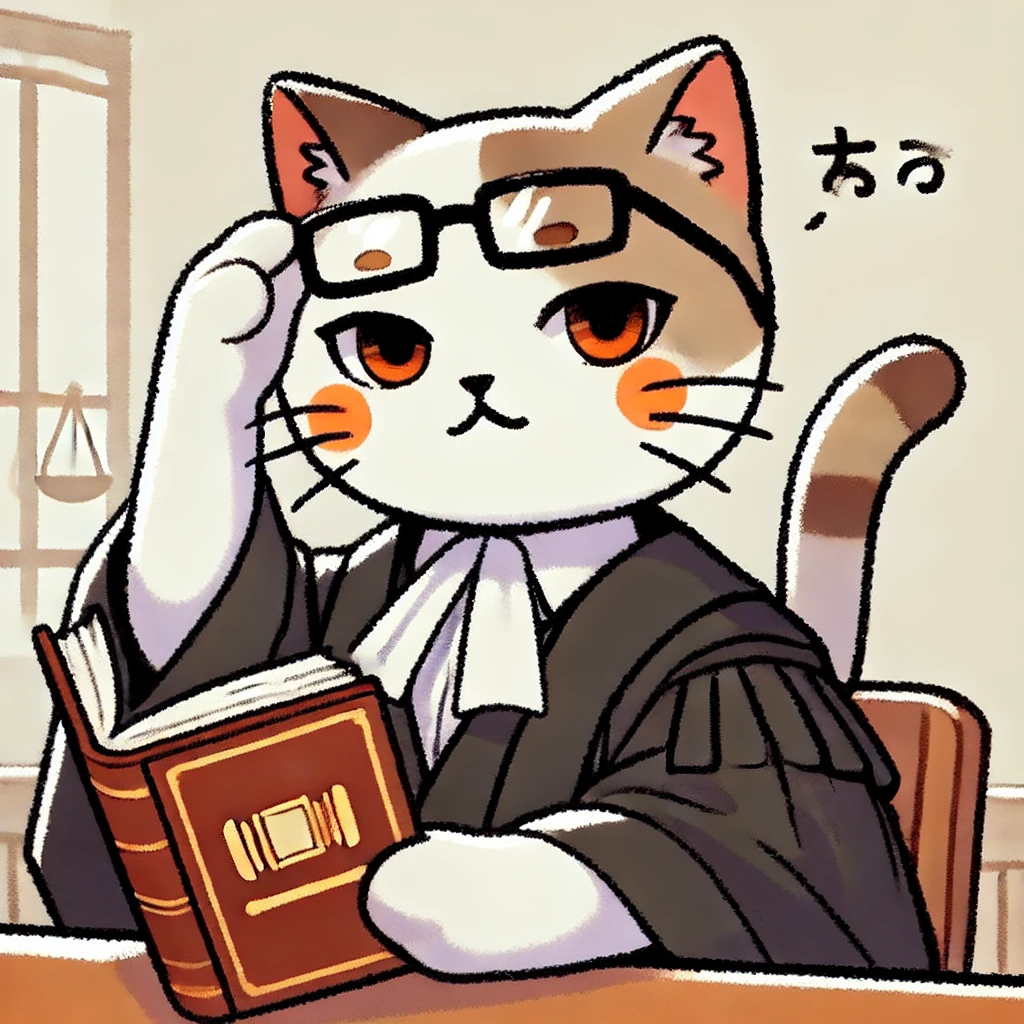
詳しくは、以下の「専門業務型裁量労働制」を参照
企画裁量型労働制
企業の中枢部で企画・立案・調査・分析の業務に従事するホワイトカラーについてのみなし時間制です(労基法38条の4)。裁量型労働制の具体的な内容は、労働基準法38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針(平成15年10月22日厚労告第353号)に規定されています。
企画裁量型労働制を採用するには、事業場の労使委員会において、5分の4以上の多数決による決議し、労基署に届出る必要があります。行政解釈では、上記の指針に違反する労使委員会決議は労基法違反とされ、みなし時間制の適用はないとされています。
裁量型労働のみなし時間の効果
労働者が実際に労働した時間にかかわらず、労使協定等で定めた時間数労働したものとみなされます。労働者は実際の労働時間を主張することはできません。
ただし、労基法の労働時間規制を全面的に排除する制度ではありません。休憩や休日、時間外・休日労働、深夜労働の規制は及びます。法定労働時間を超える時間をみなし時間と定めれば、残業代の支払が生じます。